サイト検索
検索結果
1102 件のうち 901~920 件表示
-
 緊急事態宣言期間延長にともなう講習会・セミナーの中止・延期について新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間が令和2年5月31日までに延長されたことを受け、同期間については、受講者および講師の感染リスクを考慮し、木住協主催の講習会・セミナーは実施いたしません。延期した講習会等の新たな日程は、緊急事態措置の解除後を想定しておりま...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=974
緊急事態宣言期間延長にともなう講習会・セミナーの中止・延期について新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間が令和2年5月31日までに延長されたことを受け、同期間については、受講者および講師の感染リスクを考慮し、木住協主催の講習会・セミナーは実施いたしません。延期した講習会等の新たな日程は、緊急事態措置の解除後を想定しておりま...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=974 -
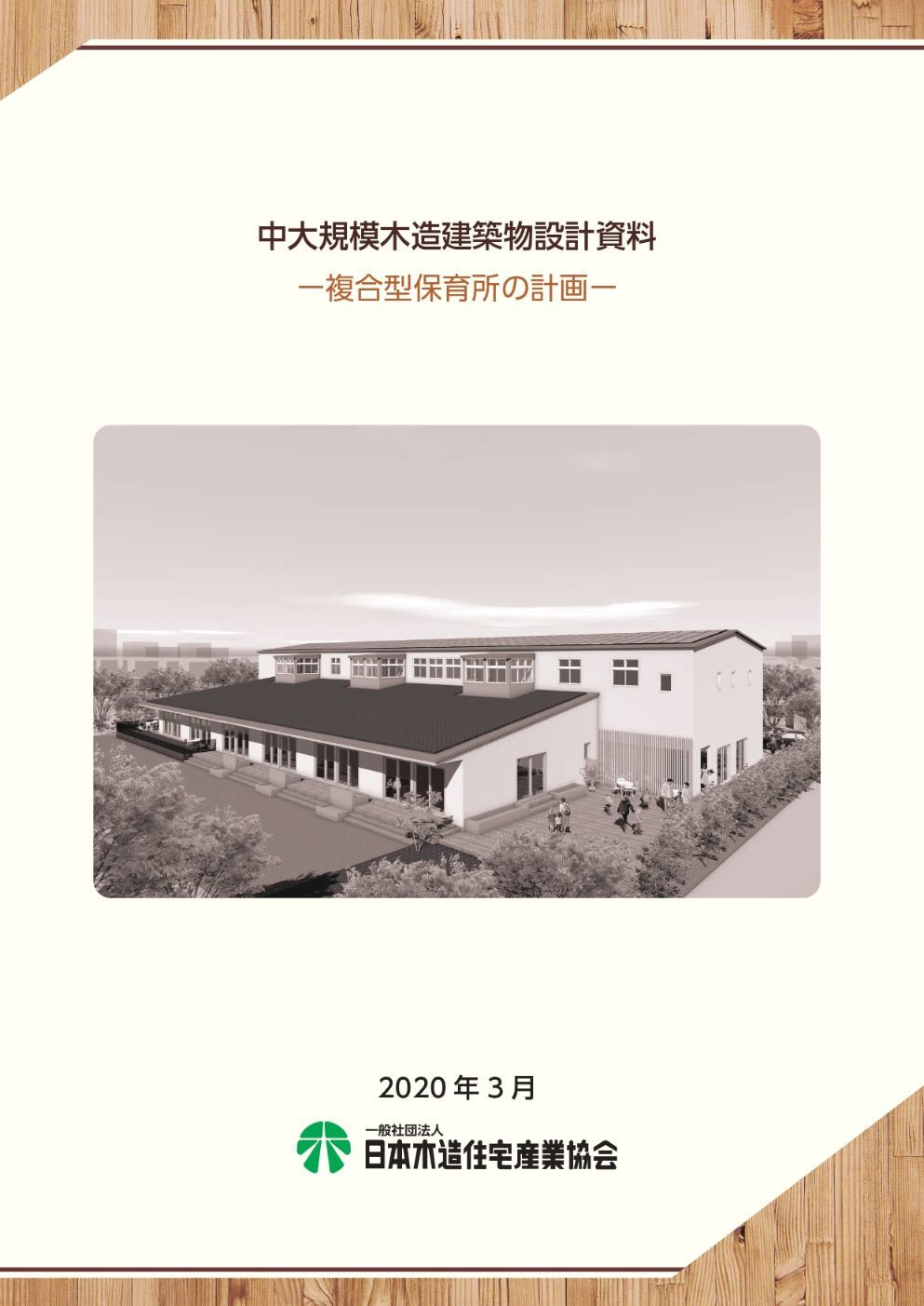 中大規模木造建築物設計資料-複合型保育所の計画-公共建築物等木材利用促進法の施行を受けて、最近特に“やさしさと温かさ”があり、“木”に触れることによる安心感がある木造による建築数が増加している幼稚園・保育所に注目し、保育所に地域社会との交流支援や子育て支援機能等を付加したこれからの保育所として「複合型保育所」を提案し、「中大規模建築物設計資料-複合...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t088
中大規模木造建築物設計資料-複合型保育所の計画-公共建築物等木材利用促進法の施行を受けて、最近特に“やさしさと温かさ”があり、“木”に触れることによる安心感がある木造による建築数が増加している幼稚園・保育所に注目し、保育所に地域社会との交流支援や子育て支援機能等を付加したこれからの保育所として「複合型保育所」を提案し、「中大規模建築物設計資料-複合...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t088 -
 令和元年度(2019年度分) 着工動向等のアンケート調査(木住協自主統計)ご協力のお願い当協会では、1種正会員各位を対象に、昨年度に引き続き31回目となる令和元年度分(2019年度分)(平成31年4月1日~令和2年3月31日)の「着工動向等のアンケート調査」を実施いたしますのでご協力をお願いいたします。詳細は以下をご覧ください。 「着工動向等のアンケート調査(木住協自主統計)」ご協力のお...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=873
令和元年度(2019年度分) 着工動向等のアンケート調査(木住協自主統計)ご協力のお願い当協会では、1種正会員各位を対象に、昨年度に引き続き31回目となる令和元年度分(2019年度分)(平成31年4月1日~令和2年3月31日)の「着工動向等のアンケート調査」を実施いたしますのでご協力をお願いいたします。詳細は以下をご覧ください。 「着工動向等のアンケート調査(木住協自主統計)」ご協力のお...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=873 -
 【会員会社限定】2020年度版「住宅と税金」~税制ガイドブック~発行のお知らせ発行を延期させて頂いておりましたが、このほど、新型コロナウイルス感染症対策(経済対策)として、国会閣議において決定した内容を盛り込み「住宅と税金」の2020年度版を発行する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。 尚、お申し込みいただきました会員会社様へは、4月27日以降、順次発送いたします。 お...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=870
【会員会社限定】2020年度版「住宅と税金」~税制ガイドブック~発行のお知らせ発行を延期させて頂いておりましたが、このほど、新型コロナウイルス感染症対策(経済対策)として、国会閣議において決定した内容を盛り込み「住宅と税金」の2020年度版を発行する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。 尚、お申し込みいただきました会員会社様へは、4月27日以降、順次発送いたします。 お...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=870 -
 2020年度「住宅税制改正セミナー」開催日時の変更について2020年度「住宅税制改正セミナー」東京会場・静岡会場の開催日時が変更となりましたのでお知らせいたします。 東京会場 ※会場の変更はありません 変更前:2020年4月20日(月) 13:25~15:40(受付13:05~13:25) 変更後:2020年5月11日(月) 9:45~12:00 (受付9:2...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=859
2020年度「住宅税制改正セミナー」開催日時の変更について2020年度「住宅税制改正セミナー」東京会場・静岡会場の開催日時が変更となりましたのでお知らせいたします。 東京会場 ※会場の変更はありません 変更前:2020年4月20日(月) 13:25~15:40(受付13:05~13:25) 変更後:2020年5月11日(月) 9:45~12:00 (受付9:2...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=859 -
 耐火建築物実例集(WEB版)発刊についてこのたび、木住協の耐火構造大臣認定書(写し)を利用して建築した住宅や中大規模木造建築物の作品集を最新版に更新しました。 当協会のホームページに掲載しましたので、是非以下アドレスよりご覧ください。【木住協HP内1時間・2時間耐火構造】木造軸組工法による耐火建築物実例集 この記事に関するお問い合わせ担当:...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=835
耐火建築物実例集(WEB版)発刊についてこのたび、木住協の耐火構造大臣認定書(写し)を利用して建築した住宅や中大規模木造建築物の作品集を最新版に更新しました。 当協会のホームページに掲載しましたので、是非以下アドレスよりご覧ください。【木住協HP内1時間・2時間耐火構造】木造軸組工法による耐火建築物実例集 この記事に関するお問い合わせ担当:...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=835 -
 愛知県・名古屋市との応急仮設住宅の建設に関する協定締結について当協会は、令和2年3月19日、災害救助法に規定する応急仮設住宅の建設協定を愛知県と名古屋市の間で締結いたしました。これは、愛知県地域防災計画に基づき、木造住宅による応急仮設住宅を迅速に建設するための協力体制を確立するものです。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。 1.締結日令和2年3月19日(木)...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=831
愛知県・名古屋市との応急仮設住宅の建設に関する協定締結について当協会は、令和2年3月19日、災害救助法に規定する応急仮設住宅の建設協定を愛知県と名古屋市の間で締結いたしました。これは、愛知県地域防災計画に基づき、木造住宅による応急仮設住宅を迅速に建設するための協力体制を確立するものです。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。 1.締結日令和2年3月19日(木)...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=831 -
 2020年度『住宅税制改正セミナー』開催のご案内2020年度『住宅税制改正セミナー』の開催が決定しましたのでご案内いたしますのでふるってご参加ください。プログラム13:25~13:30主催者挨拶13:30~15:40「住宅と税金」について講師:税理士法人下平・櫻井事務所(木住協顧問税理士)15:40閉会詳細・お申込は下記講習会WEB申込システムを...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=805
2020年度『住宅税制改正セミナー』開催のご案内2020年度『住宅税制改正セミナー』の開催が決定しましたのでご案内いたしますのでふるってご参加ください。プログラム13:25~13:30主催者挨拶13:30~15:40「住宅と税金」について講師:税理士法人下平・櫻井事務所(木住協顧問税理士)15:40閉会詳細・お申込は下記講習会WEB申込システムを...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=805 -
 「建築基準法の一部を改正する法律」(2019年6月25日施行)【建築物の防・耐火構造における改正の概要】解説資料の公開昨年6月に施行された改正建築基準法において、建築物の防・耐火構造における改正の要点を図解で分かりやすくまとめた資料を会員向けに公開します。ID・PWを入力してダウンロードしていただき、ご活用ください。 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が2019年6月25日に施行されました。改...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=791
「建築基準法の一部を改正する法律」(2019年6月25日施行)【建築物の防・耐火構造における改正の概要】解説資料の公開昨年6月に施行された改正建築基準法において、建築物の防・耐火構造における改正の要点を図解で分かりやすくまとめた資料を会員向けに公開します。ID・PWを入力してダウンロードしていただき、ご活用ください。 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が2019年6月25日に施行されました。改...https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=791 -
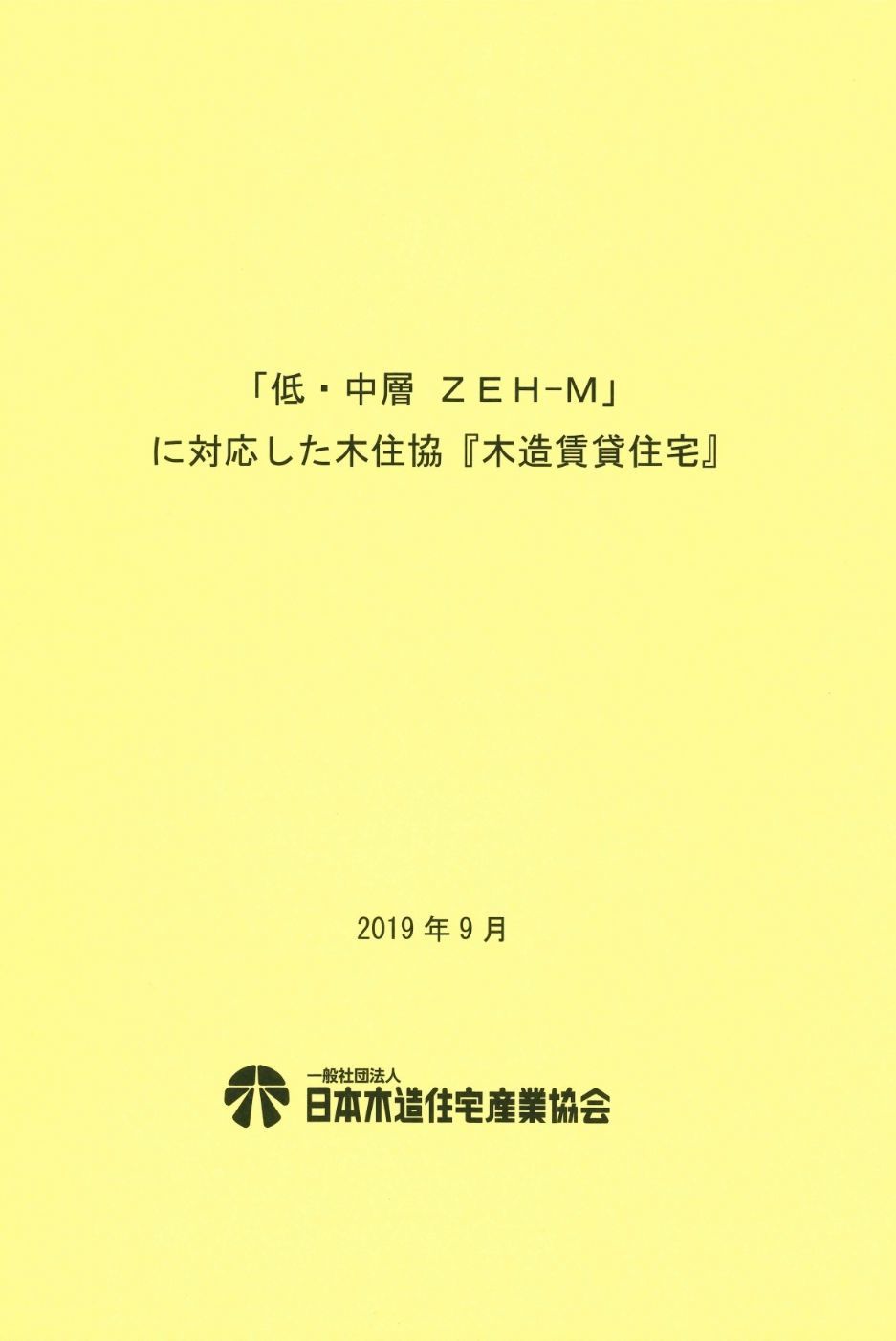 「低・中層ZEH-M」に対応した木住協『木造賃貸住宅』2016年に発行された「パリ協定」を踏まえて、我が国では住宅建築物の省エネルギー対策が強化され、2019年度以降、建売戸建住宅に関する省エネ性能向上のための基準として「住宅事業建築主基準」が施行されてきましたが、今般、「注文戸建住宅」及び「賃貸アパート」を供給する大手住宅事業者が対象に加わる改正がなさ...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t087
「低・中層ZEH-M」に対応した木住協『木造賃貸住宅』2016年に発行された「パリ協定」を踏まえて、我が国では住宅建築物の省エネルギー対策が強化され、2019年度以降、建売戸建住宅に関する省エネ性能向上のための基準として「住宅事業建築主基準」が施行されてきましたが、今般、「注文戸建住宅」及び「賃貸アパート」を供給する大手住宅事業者が対象に加わる改正がなさ...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t087 -
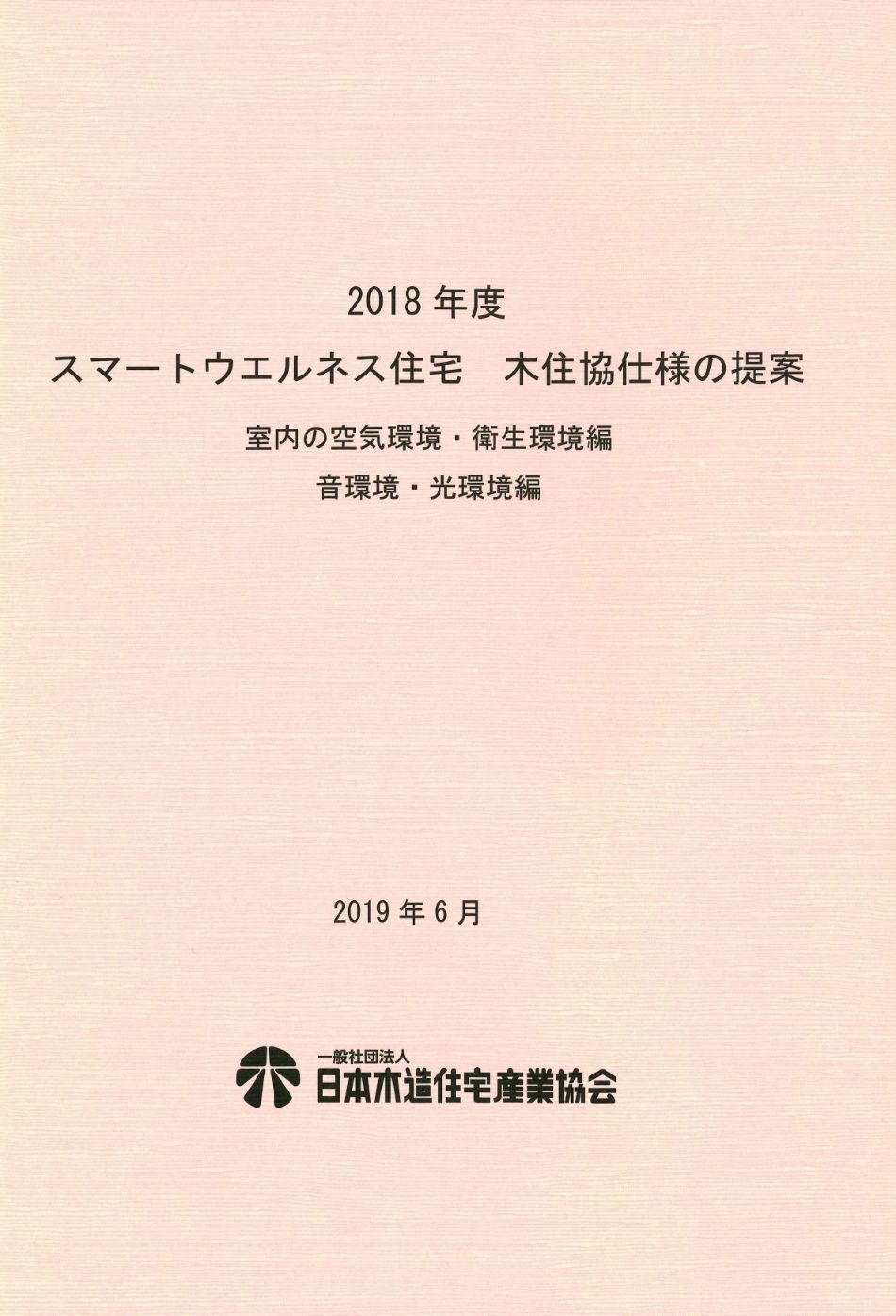 2018年度 スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 室内の空気環境・衛生環境編 音環境・光環境編「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案」として、2016年度に「高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を、2017年度に「温熱環境・木質環境編」を発行しました。 続いて2018年度は第3弾として、室内空気の清浄保持による居住者の健康・快適性について整理した 「室内の空気環境・衛生環境編」と、生活騒...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t086
2018年度 スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 室内の空気環境・衛生環境編 音環境・光環境編「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案」として、2016年度に「高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を、2017年度に「温熱環境・木質環境編」を発行しました。 続いて2018年度は第3弾として、室内空気の清浄保持による居住者の健康・快適性について整理した 「室内の空気環境・衛生環境編」と、生活騒...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t086 -
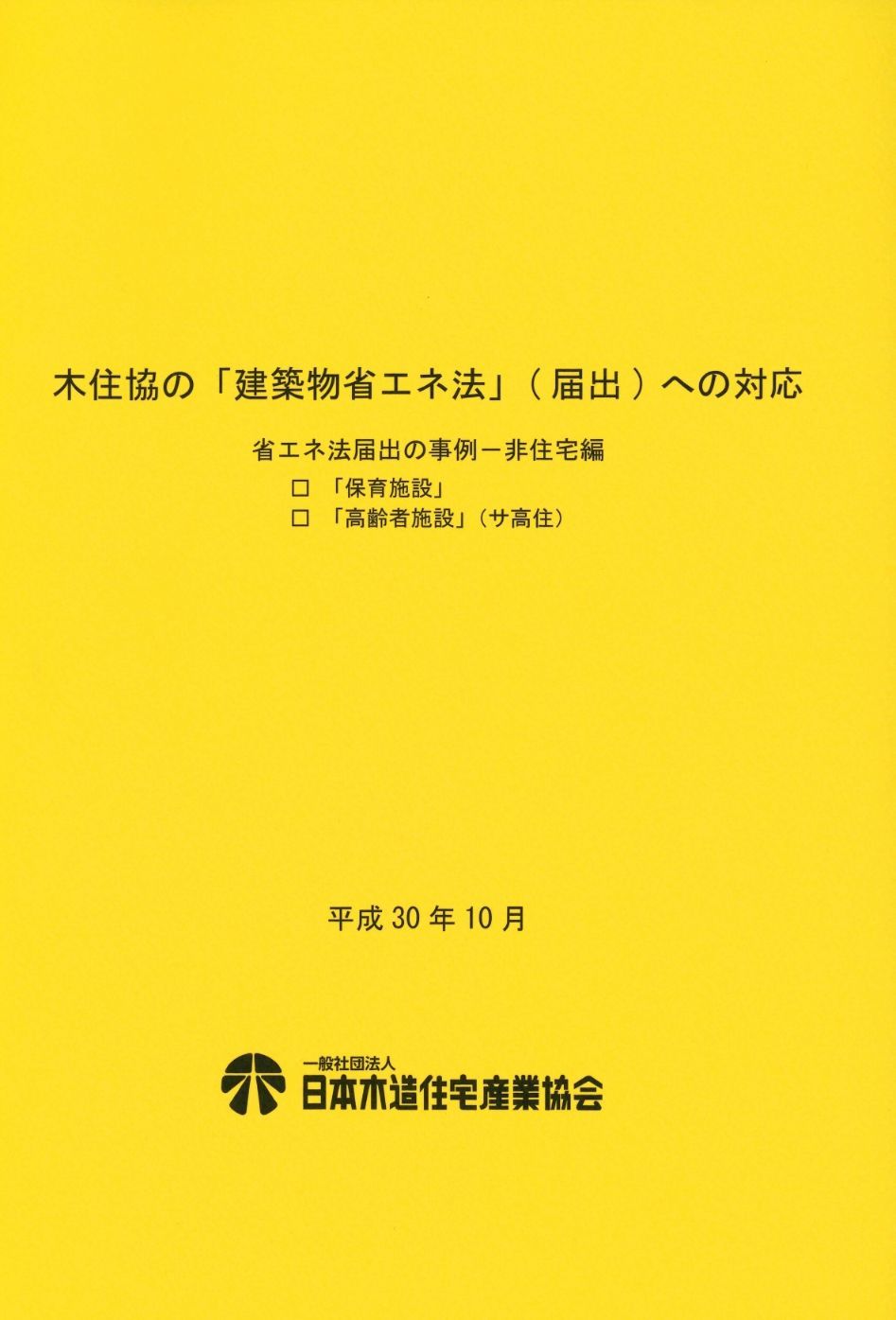 木住協の「建築物省エネ法」(届出)への対応 省エネ法届出の事例-非住宅編 □「保育施設」 □「高齢者施設」(サ高住)建築物省エネ法(平成27年7月公布)により、大規模な非住宅建築物に対するエネルギー消費性能基準への「適合義務」や、中規模の建築物に対する「届出」義務等の規制的措置が施行されました。木住協では、「中規模以上の建築物に対する届出義務」に着目し、木造3階建て共同住宅を具体的な事例として取り上げ、平成30年3...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t085
木住協の「建築物省エネ法」(届出)への対応 省エネ法届出の事例-非住宅編 □「保育施設」 □「高齢者施設」(サ高住)建築物省エネ法(平成27年7月公布)により、大規模な非住宅建築物に対するエネルギー消費性能基準への「適合義務」や、中規模の建築物に対する「届出」義務等の規制的措置が施行されました。木住協では、「中規模以上の建築物に対する届出義務」に着目し、木造3階建て共同住宅を具体的な事例として取り上げ、平成30年3...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t085 -
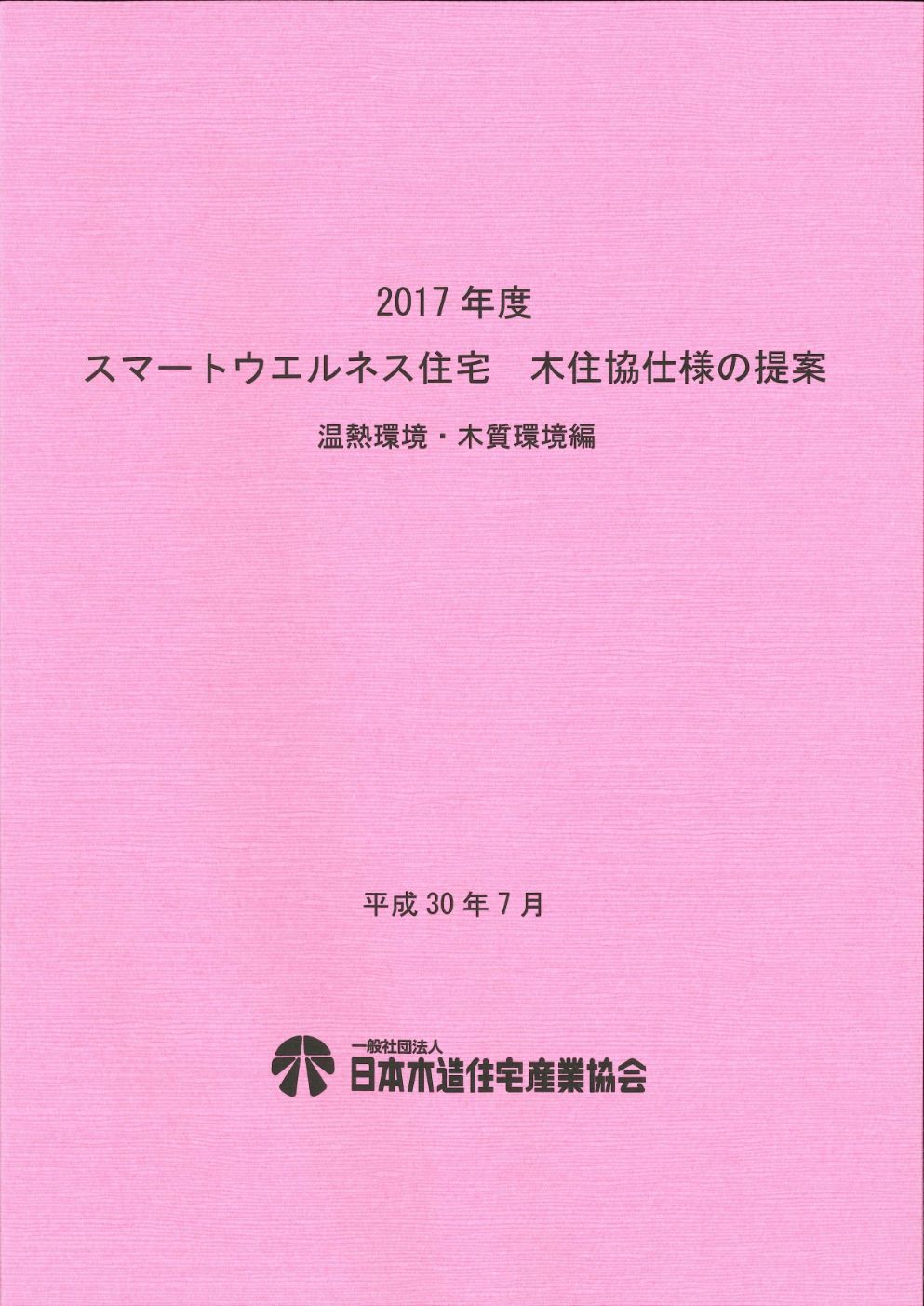 2017年度 スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 温熱環境・木質環境編2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t084
2017年度 スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 温熱環境・木質環境編2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t084 -
 あなたのお家が貯めるCO2の量を計算してみませんか?2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基.../initiative/carbon-simulate/#cpd-menu2
あなたのお家が貯めるCO2の量を計算してみませんか?2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基.../initiative/carbon-simulate/#cpd-menu2 -
 木住協は、「安心R住宅」の標章使用許諾を行う事業者団体です。2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基.../initiative/anshinr/
木住協は、「安心R住宅」の標章使用許諾を行う事業者団体です。2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基.../initiative/anshinr/ -
 会員様限定!木住協のお得な各種保険をご紹介2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基.../initiative/insurance/
会員様限定!木住協のお得な各種保険をご紹介2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基.../initiative/insurance/ -
 既存住宅状況調査技術者講習について2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基.../initiative/inspection/
既存住宅状況調査技術者講習について2016年度に「スマートウエルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編」を発行しましたが、2017年度は第2弾として、国土交通省の調査事業の成果等を踏まえ、「室内の温熱環境と人体的影響」について取りまとめ、「平成25年省エネルギー基準」の解説にある「戸建住宅のモデルプラン」を基.../initiative/inspection/ -
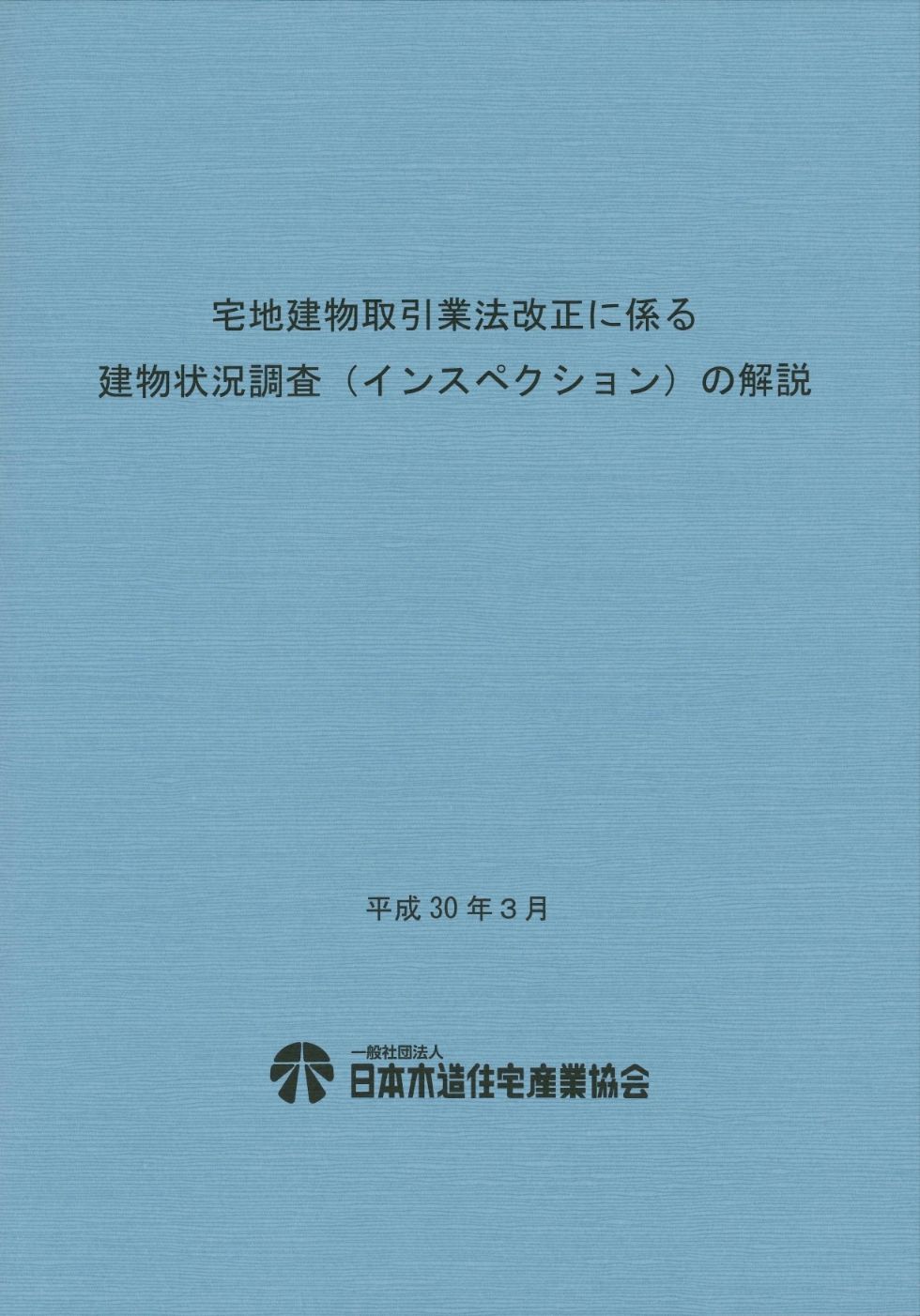 宅地建物取引業法改正に係る 建物状況調査(インスペクション)の解説既存住宅の売買取引において、売主が建物の各種情報を提供することや瑕疵担保責任を負うことが困難な状況であり、買主は住宅の質に対する不安を抱えていることが一般的です。このため、個人間売買の仲介を行う宅建業者が専門家による建物状況調査の活用を促すことで売主・買主が安心して既存住宅の取引ができる市場環境を整備...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t082
宅地建物取引業法改正に係る 建物状況調査(インスペクション)の解説既存住宅の売買取引において、売主が建物の各種情報を提供することや瑕疵担保責任を負うことが困難な状況であり、買主は住宅の質に対する不安を抱えていることが一般的です。このため、個人間売買の仲介を行う宅建業者が専門家による建物状況調査の活用を促すことで売主・買主が安心して既存住宅の取引ができる市場環境を整備...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t082 -
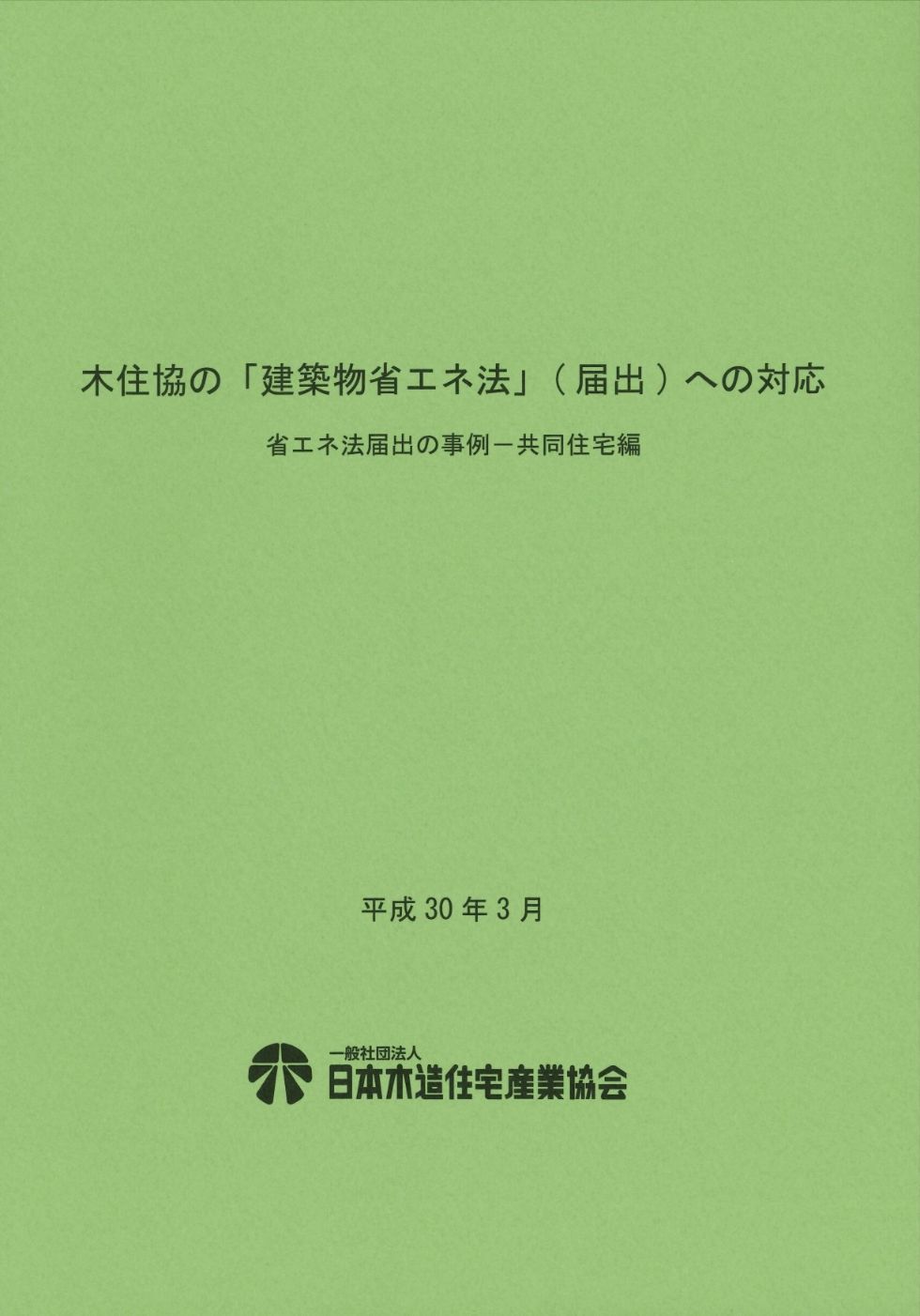 木住協の「建築物省エネ法」(届出)への対応 省エネ法届出の事例-共同住宅編建築物省エネ法(平成27年7月公布)により、大規模な非住宅建築物に対するエネルギー消費性能基準への「適合義務」や、中規模の建築物に対する「届出」義務等の規制的措置が施行されました。木住協では、「中規模以上の建築物に対する届出義務」に注目し、法律の概要及び共同住宅、事務所等の非住宅建築物、複合用途建築物...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t081
木住協の「建築物省エネ法」(届出)への対応 省エネ法届出の事例-共同住宅編建築物省エネ法(平成27年7月公布)により、大規模な非住宅建築物に対するエネルギー消費性能基準への「適合義務」や、中規模の建築物に対する「届出」義務等の規制的措置が施行されました。木住協では、「中規模以上の建築物に対する届出義務」に注目し、法律の概要及び共同住宅、事務所等の非住宅建築物、複合用途建築物...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t081 -
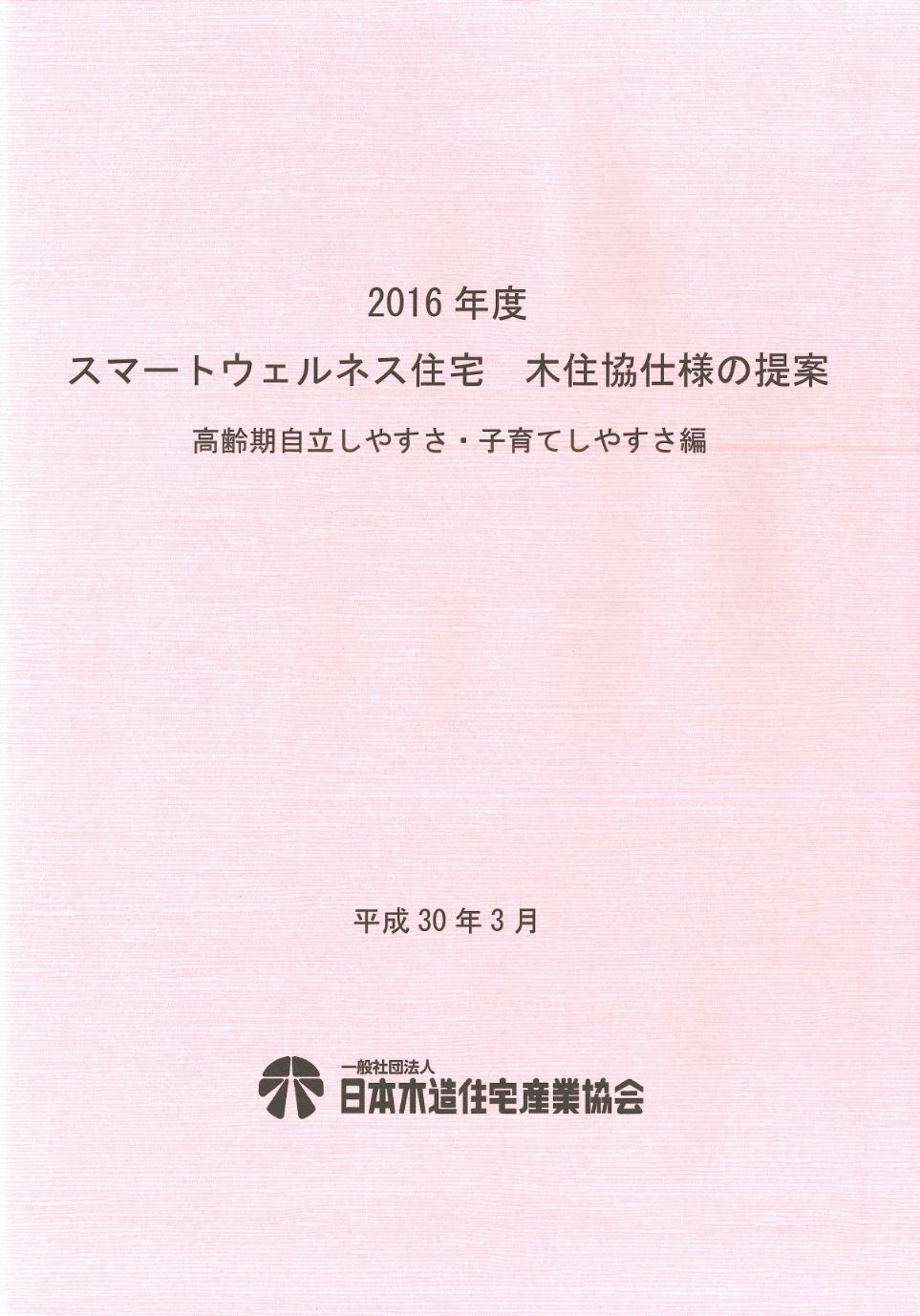 2016年度 スマートウェルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編「スマートウェルネス住宅」とは、高性能な住宅と効率的なサービス等、高齢者・障害者・子育て世帯等の多様な世代が安心・安全で健康に暮らすことができる住まいで、「人と環境にやさしい家」のことをいいます。木住協はこれをキーワードに、住宅の基本性能の確保に加え、木質空間の居心地や子育てのしやすさ、三世代居住、地...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t080
2016年度 スマートウェルネス住宅 木住協仕様の提案 高齢期自立しやすさ・子育てしやすさ編「スマートウェルネス住宅」とは、高性能な住宅と効率的なサービス等、高齢者・障害者・子育て世帯等の多様な世代が安心・安全で健康に暮らすことができる住まいで、「人と環境にやさしい家」のことをいいます。木住協はこれをキーワードに、住宅の基本性能の確保に加え、木質空間の居心地や子育てのしやすさ、三世代居住、地...https://www.mokujukyo.or.jp/books/t080



