令和2年9月8日 「建築物における木材利用の現状と施策」について 林野庁 林政部木材利用課 課長補佐 小木曽 純子 氏
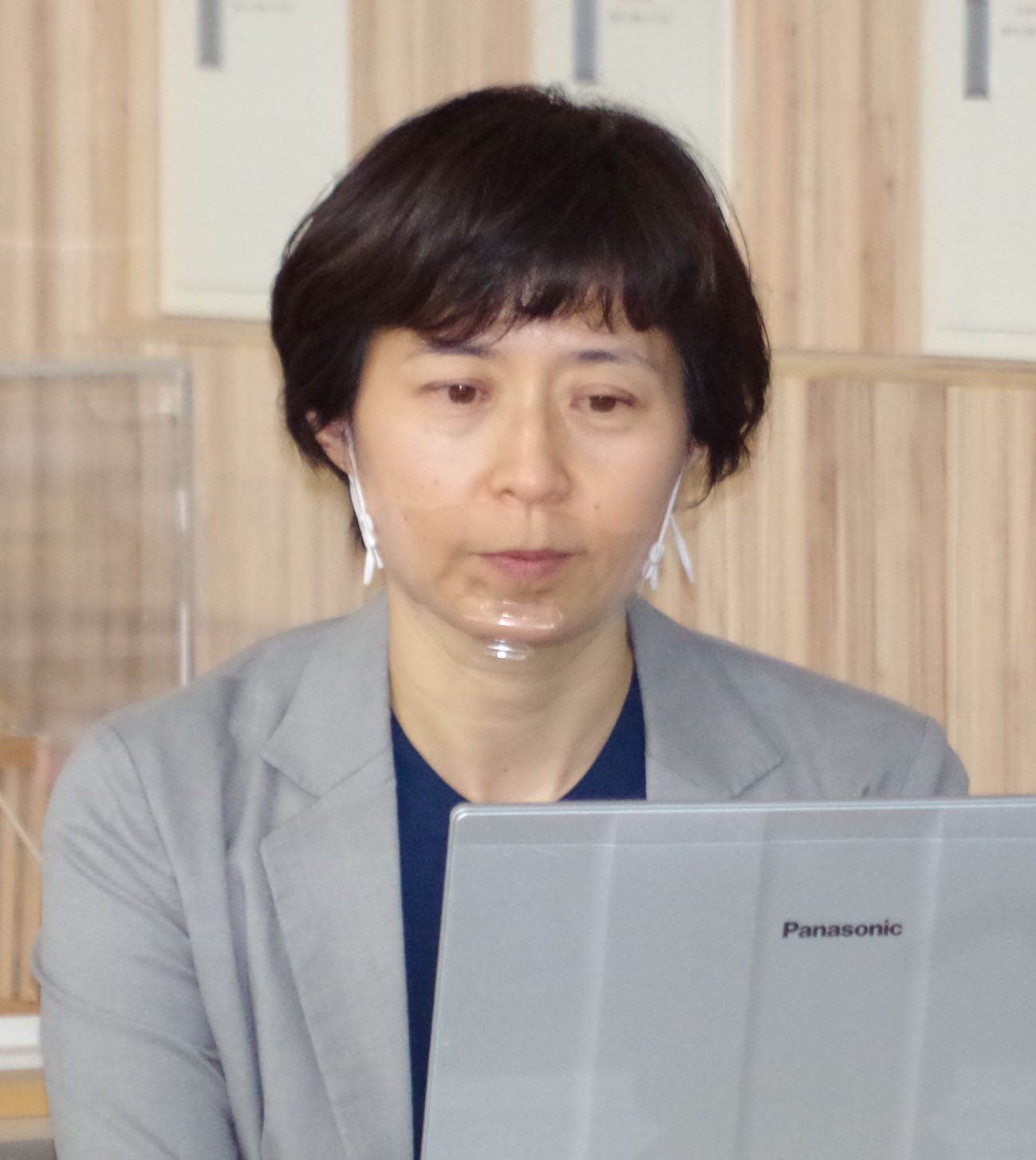
資材・流通委員会(澤田知世委員長)は、令和2年度 第2回の「住まいのトレンドセミナー 第1部」を9月8日に開催し、林野庁の小木曽純子・林政部木材利用課課長補佐(木造公共建築物促進班)が「建築物における木材利用の現状と施策」をテーマに講演しました。
小木曽・林野庁木材利用課長が「建築物に於けつ木材利用の現状と施策」を講演
小木曽課長補佐は森林資源の現状や公共建築物等における木材利用の状況などを解説したのに続き、木材利用促進に向けて昨年2月に建設事業者や設計事業者、建築物の施主となる企業などで発足した「民間建築物等における木材利用促進に向けた懇談会」
(通称:ウッド・チェンジ・ネットワーク)の目的や活動内容などについて説明しました。
我が国の森林蓄積量は現在約52億㎥に達し、戦後に植林された人工林は主伐期を迎えています。この森林資源を「伐って、使って、植える」サイクルで循環的に利用する取り組みが重要になっています。木材は製材や合板、チップに活用されていますが、
利用拡大の余地はまだ多いのが現状。小木曽課長補佐は「人口減少から新設住宅着工戸数の減少が見込まれ、低層住宅では外材から国産材への切り替え、中高層住宅や非住宅建築物では木材利用の一層の促進が求められます」と述べ、住宅と非住宅建築物
への利用拡大の必要性を強調しました。
公共建築物等木材利用促進法の成立(平成22年)や建築基準法改正による木材利用の推進、木材利用促進の予算措置、官民や地域における各種整備事業の推進などによって、各地で木材を活用した公共建築物が竣工しています。小木曽課長補佐も岩手県大槌町 の文化交流センター「おしゃっち」や沖縄県宮古島市のみやこ下地島空港ターミナル、東京都品川区の東急池上線戸越銀座駅などの事例を紹介し、「木材を建築物に利用することは、低コスト・短工期化などビジネスにおける効果のほか、地球温暖化対策へ の貢献、地方創生の実現など社会的課題解決に向けた効果という3つの意義があり、今まで以上に木材利用を積極化したい」と述べました。
また、民間建築物における木材利用促進のため設置されたウッド・チェンジ・ネットワーク(WCN)は、建築主となる企業や、建設事業者、設計事業者、関係団体、学識経験者、行政で構成されており、木住協会員社の住友林業やポラス、ナイス、シェルター も建設事業者に名を連ねています。懇談会では、①木造のイメージをチェンジ②低層非住宅・中高層建築物を木造にチェンジ③持続可能な社会へチェンジ――を目的に、木材利用に関する課題の特定や解決方策、木材利用に向けた普及の在り方などを協議・ 検討し、全国に木材利用を広げていくプラットホームづくりに取り組むことにしています。
WCNでは①低層小規模②中規模ビル③木質化のワーキンググループ(WG)を設けて課題解決に向けた検討をしています。このうち低層小規模WGでは昨年度コンビニエンスストアや事務所など低層小規模店舗を想定した柱のない複数の木構造について、 工事日数やコストなどを整理されました。また、中規模ビルWGでは中規模ビルの木造化事例の収集やニーズの抽出を、木質化WGでは木質化事例を収集して用途と木質化した効果の関連を整理した事例集が作成されたところです。
小木曽課長補佐は、「公共建築物等木材利用促進法の成立以降、建築物などにおける木材利用が進展しており、近年にはさまざまな分野において木材利用の取り組みが展開されています。植林後下刈り・間伐を行い、主伐した木材を適材適所で利用し、 あらゆるところをウッドにチェンジすることで森林の持続的なサイクルを構築して、林業の成長産業化と森林の適切な管理に向けて取り組みを進めていきたい」と語りました。



